| 笹之雪と根岸ミニ散歩 -2025.11.9- |
| 久しぶりの富岡八幡宮 -2025.7.13- |
| 築地で「発祥の地」の碑巡り -2025.2.23- |
| 皇居乾通秋の通り抜け -2023.12.3- |
| 新橋-浜松町・竹芝散策 -2023.11.23- |
| 秋の古河庭園・牧野記念公園 -2023.11.9- |
| 赤坂離宮迎賓館 -2023.5.7- |
| 笹之雪と根岸ミニ散歩(台東区) (獏塾友の会結成10周年食事会)-2025.11.9- |
||||||||
|
||||||||
| 日暮里駅西口集合。駅名は猫フォント。「暮」の草冠の上は猫の耳。「駅」の四ツ点は猫の肉球で、跳ねの先はしっぽ | 笹之雪は元禄4年創業。この家の娘が赤穂浪士と恋仲だったとか。河鍋暁斎や正岡子規も贔屓にしていました | 一緒に江戸検定の勉強をしたお仲間で作った「獏塾友の会」が10周年を迎えたのでちょっと豪華な食事会 | ↑は子規庵。笹之雪は昨年、新店舗に移転しました。笹之雪と縁の深い、子規庵のお隣の土地です | 子規庵の向かい側は書道博物館。ここは正岡子規と深い親交のあった画家、書家の中村不折旧宅跡 | 王子街道に面した茶屋の「羽二重団子」は子規の俳句にも詠まれました。「芋坂も団子も月のゆかりかな」 | 善性寺は6代家宣の生母長昌院が葬られた徳川ゆかりの寺。上野戦争の際に彰義隊の屯所となりました | ||
| 久しぶりの富岡八幡宮(江東区) -2025.7.13- |
||||
| 2023の震災の時訪ねた富岡八幡宮。あの時割れていた石灯篭は無くなっていました | 陶器市で賑わう境内はあの時と同じ。違うのは外国人観光客がとても多いこと | 参道を入ってすぐの伊能忠敬像。いつも富岡八幡で無事を祈って遠国に出発したそうです | 昭和39年無形文化財に指定された木場の角乗の碑。角乗は木場公園で秋に披露されています | |
|
||||
| 奥に見える合末社は空襲による焼失を免れましたが鳥居は爆弾の直撃で上部がありません | 横綱力士碑は明治33年第12代横綱陣幕が発起人となり建立されたものです | 本殿の奥には弁天池と、やはり戦災を免れた弁天社、花本社があります | 花本社は松尾芭蕉を祀ったお社です。「ご祭神・芭蕉命」とあります | |
| 築地で「発祥の地」巡り(中央区)-2025.2.23- | ||||||||
 |
 |
 |
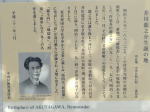 |
|
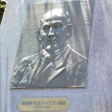 |
 |
||
| 私の母校雙葉学園発祥の地。最初は語学や西洋作法を教える女子塾でした | 東京中学院発祥の地。現関東学院の源流です | 浅野内匠頭邸跡。浅野家の広大な上屋敷がありました | 芥川龍之介生誕の地。彼はこの付近の牧場主の息子に生まれました | 築地外国人居留地跡。左は当時珍しい街頭ガス灯。柱は当時のものです | 聖路加病院創設者トイスラ―医師のレリーフ | 聖路加病院の敷地には「トイスラ―記念館」が建っています | ||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
||
| アメリカ公使館跡の石標。明治8年、港区の善福寺からこの地に移りました | 立教学院発祥の地。立教も立教女学院もウィリアムズ主教が開校 | 立教女学院の碑。湯島に設立されこの地に移転、今は久我山に | 築地本願寺にある九条武子の歌碑。武子は京都女子専門学校(京都女子大)の設立者です | 備前橋跡。築地川は今は殆ど埋め立てられており、暁橋、境橋、門跡橋など石標のみ | あかつき公園のシーボルト像。娘いねの産院は築地にありました | 勝鬨の渡し跡。昭和15年に橋ができるまで渡船場でした。後ろは「勝どき橋之資料館」 | ||
| 皇居乾通秋の通り抜け(千代田区)-2023.12.3- | |||
 |
 |
 |
 |
| 一般公開最終日。二重橋濠の横を通り、手荷物と身体検査を受けて入りました | 坂下門から。東御苑や宮殿参観コースは歩いたことがありますが、ここは初めて | 今年は紅葉が遅く、実は緑が多かったけど紅葉している樹は青空に映えて綺麗 | 蓮池参集所。陛下が賢所清掃奉仕団の人達から挨拶を受ける建物だそうです |
 |
 |
 |
|
| 秋に咲く桜、コヒガンの仲間のシキザクラが咲いていました。 | 明治6年女官部屋からの出火で西の丸御殿は全焼。↑は明治20年築の局門。 | 新しい宮殿が建てられたのは明治22年でした。↑は明治20年に建てられた門長屋 | 乾門から退出。北の丸のイチョウはすっかり色づいていました。 |
| 新橋―浜松町竹芝散歩(港区)-2023.11.23- | ||||
| 港区観光大使で芝会議・まちの魅力発掘部会サブリーダーのN氏は江戸文化歴史検定一級(私は彼の先輩なのだ、エヘン)の知識を生かして港区のボランティアガイドとして活躍中。今回、江戸検のお仲間に、新橋~浜松町竹芝の面白いスポットを案内して下さいました。この周辺は少し前から再開発が行われることが多く、その際に鉄道や大名屋敷の遺構が発掘されることで、歴史的に意義のある発見が相次いでいます。 | ||||
 |
 |
 |
 |
 |
| 集合は新橋SL広場。このC11 292型SLは1972年に鉄道開業100周年を記念して設置されました | 烏森口から反対側に渡ると「鉄道唱歌の碑」♪汽笛一声新橋を~。399番プラス満州まであるとか | 旧新橋停車場跡。明治5年に建てられ、震災で焼失。平成3年の発掘調査の結果再建されました | 汐留通りに戻り南下すると左手に近代的な日テレタワーが現れます。周囲も高層ビルだらけですけど。 | ここはもと陸奥仙台藩伊達家の上屋敷。↑は案内板にあった広重の「江都勝景」。文政7年の大火後なので冠木門 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 新橋4丁目にある日比谷神社。伊達家の敷地内にありましたが、維新、鉄道敷設、戦争、再開発で移転また移転の運命 | おやここは日本?道路は石畳、ビルにはバルコニー。この辺りをイタリア風にすることで新橋の個性にしています | 慶應義塾、攻玉社の学塾跡。どちらも後に移転。「発祥の地」は築地なのでこれは「命名の地」だそうです | 海側に向かう道に面して赤穂藩森家の石垣が一部残っています。境堀の護岸のもので、もう少し高さがあったようです | 東新橋に一文銭などの銭を作る芝新銭座がありました。JRのガード下張り紙にのみ、その名が残っています |
 |
 |
 |
 |
 |
| ガードをくぐるとイタリア公園を経て東京湾に出ます。↑竹芝ふ頭からのウォーターフロントのタワマン群 | 竹芝ふ頭公園には船に関する文字タイルが。「舟偏に義」は「フナヨソオイ」、舶の訓読みは「オオフネ」 | 南に目をやるとレインボーブリッジやお台場。この上の展望台は元旦には初日の出撮影の人で大混雑とか | 浜松町駅に向かう歩行者デッキがあります。首都高速道路も芝離宮恩賜庭園(↑)も上から見下ろせます | なんと!神戸や長崎からも江戸検のお仲間が参加して歩きました。浜松町駅近くの居酒屋で宴会です |
| 上のコースは Youtubeで「教えて!港区ボランティアガイド」と検索すれば、N氏と文化放送の西川文野アナが港区を散歩する動画で見ることができます。第1回~第5回まであります。Nさんのわかりやすい解説に女子アナも納得! | ||||
| 秋の古河庭園・牧野記念公園(北区・練馬区)-2023.11.9- | |||||
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| 秋のバラフェスティバル中の古河庭園 。秋のバラは春より小ぶりですが色も香も濃厚です | 「プリンセスミチコ」は皇太子妃だった上皇后さまに捧げられたバラ。蛍光色のような朱 | 愛子内親王に捧げられた「ロイヤルプリンセス」は甘い香りが強く漂っていました | 美しいピンク色のシャルル・ド・ドゴール | 日本庭園では雪吊りの作業中でした。上は心字池。この後紅葉の季節になります | 色づいている樹木もありました。樹下には可愛いドングリが沢山落ちていました。 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
| ずっと行ってみたかった牧野記念庭園。NHK朝ドラ「らんまん」は牧野富太郎がモデルです | 上は「いちりんそう」の名札が差してありましたが「ノコンギク」のようです | 上は「ヒトツバヒイラギ」の花。柊特有の葉っぱのギザギザもトゲもない珍しいものです | 前回の特別展チラシにあったリンボクの植物画 | 再現された書斎には「牧野博士は今庭にジョウロウホトトギスを見に行きました」と札が! | ドラマにも出てきた仙台屋の庭の「センダイヤザクラ」も博士の命名。ねりまの名木です |
| 赤坂離宮迎賓館 (港区)-2023.5.7- | ||||||
| 迎賓館はご存じの通り、もと紀州徳川家の中屋敷。廃藩後用地は皇室に献上され、M42東宮御所として洋館が建設されました。設計はジョサイア・コンドルの4人の弟子のうちの一人片山東熊。ともかく地震に強い建物をということで、建物全体の3分の1は壁材ではないかというくらい。最も薄い壁でも30cm近い厚みがあるそうです。関東大震災にもびくともせず、シャンデリアが落ちることもありませんでした。戦後は国に移管され、S49に修復を経て迎賓館として国賓を迎える外交の舞台となりました。H21には本館、正門、噴水等が明治以降の建物としては初めての国宝に指定されています。内部は撮影禁止なので下段の写真はパンフレットです。 | ||||||
 |
 |
 |
 |
 |
||
| 四ツ谷駅に集合し、駅そばの中華料理店でランチをとってスタート。↑の正門ではなく西門から入ります | 入園するのに金属探知機による手荷物検査が必要でした。ざんざん降りの雨の中、律儀に噴水が噴出中 | 先ず和風別館「游心亭」でガイド付見学。前庭や天井、壁、床の説明から様々なエピソード等、興味深く聴きました | 次に本館へ。すごい雨でしたが、中に入るとバロック調でありながら和の意匠をちりばめた豪華な賓室は別世界 | 本館前で外国人旅行客と思しきご夫婦に頼んで集合写真を撮りました。 | ||
 |
|
 |
 |
|||
| 最も格式の高い「朝日の間」は東宮御所として建てられた時は食堂だったそうです | 馬車に乗った女神が朝日の中を行く天井絵が朝日の間の由来です。H31に修復完成 | 「花鳥の間」には30枚の七宝焼の花鳥が飾られています。シャンデリアの上は油彩画。 | 游心亭の主和室。晴れていると真下の池の水が天井にゆらめきを映し出すそうです | 茶室は外国の賓客にも茶道の雰囲気を楽しめる様にサイズも造りも工夫されています | ||
| ホームへ |


















